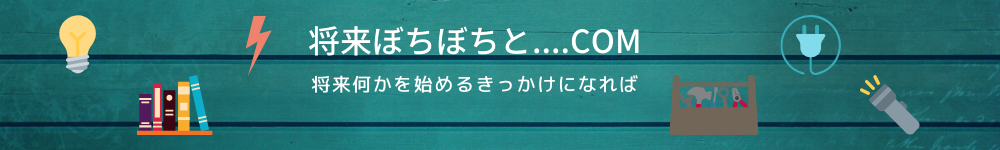ラダー図で誤動作の原因となる2重コイルは避ける!

PLCラダー図を作成する場合に2重コイルはダメだと教えられている人も多いかと思います。
私も2重コイルはダメだと教えられているので他の命令でも2重コイルと勘違いして使用しなかったりした時がありました。
今回はラ ...
ローラーチェーンでのジョイントクリップ方向に注意する!

機械の駆動(回転)部分にはローラーチェーンがついていて、工場ではコンベアなど搬送させたい部分によく使用されているかと思います。
搬送部分が動かなくなった時はローラーチェーンの伸び、破損、錆などが原因で動かなくなる場合があり ...
ブレーカのMCB、MCCB、NFB、ELB、ELCBの違いとは?わかりやすく解説!

電気図面で使用されているブレーカの文字記号にMCCBやNFBまたELCBなどが表記されているのを見たことがあるかと思います。
これらの意味をしっかり理解されているでしょうか?
ブレーカは過電流や漏電など不具合が ...
ボルトに入れる平ワッシャーやスプリングワッシャーの役割とは?順番もある?わかりやすく解説!

機械にはボルト、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを組み合わせてとりつけている場合を見ることがあるかと思います。
この平ワッシャーやスプリングワッシャーにはそれぞれ役割があり、とりつける順番もあります。
PLCラダー図の内部リレーMの使い方!出力リレーYとの違いとは!?

PLCラダー図ではプログラム上で使用できる内部リレーがあり、この内部リレーを利用してたくさんの条件を組んでいくことができます。
ですが、内部リレーの使い方を知らないと、完成後に回路を確認しようとしてもわかりにくい回路となっ ...
シングルソレノイドバルブとダブルソレノイドバルブの違いとは?ラダー図も使って説明!

シングルソレノイドバルブとダブルソレノイドバルブの違いについて理解されているでしょうか。
この2つは工場の生産現場では必ずといっていいほどよく使われているので動きをよく知っておかなければいけません。
動きを知っ ...
シーケンス制御のインターロック回路とは?シーケンス図やラダー図を使ってわかりやすく紹介!
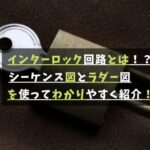
シーケンス制御を最初に学んでいると『インターロック回路』という言葉を聞くことが多いかと思います。
このインターロック回路は機械の破損や人に危険を及ぼさないために使用され、シーケンス制御には、欠かすことのできない基本回路の1 ...
【第2種電気工事士】抵抗率と導電率の違いとは?また電線の抵抗・長さ・太さの関係!

第2種電気工事士の試験勉強をしているとまずこの抵抗率と導電率といったよく似た言葉が出てくるかと思います。
試験にもよく出題されるのでこの2つの意味をしっかり覚えておきましょう。
また電線の抵抗・長さ・太さを求め ...
制御盤の配線に線番号がいる理由とは!?線番号の決め方や向きにも注意が必要!

制御盤には線番号がついたマークチューブというものが電線ごとについています。
配線する時にはこの線番号を決めて配線をしていくのですが、どのように番号をつけていくのか最初は悩むかと思います。
またマークチューブの向 ...
一般家庭の分岐回路とは?許容電流や電線の太さについてもわかりやすく説明!

一般家庭の分電盤でブレーカや電線はどのように選定され、分岐回路から配線されるか理解されているでしょうか。
分岐回路には種類があり、それぞれのブレーカの定格電流、接続できるコンセントの定格電流、電線の太さが決められています。 ...